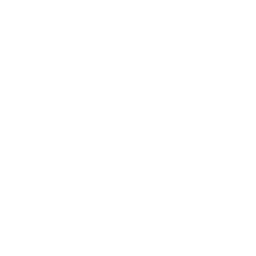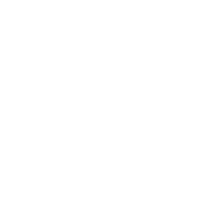精神疾患があっても生活保護の申請は可能なのかと疑問に思ってはいませんか?この記事では、生活保護に年齢や病名による制限があるのかどうか、申請ができる場合のポイントについて解説します。
1.受給条件に病名や年齢の制限はない

生活保護の受給資格は、世帯の収入が厚生労働省が定める「最低生活費」を下回っているかどうかという経済状態のみで判断されます。年齢や健康状態、病名による制限は一切なく、生活に困窮している人であれば、誰でも申請が可能です。
生活保護は怪我や病気で働けない人、乳幼児を育てているシングルマザー、親族の介護をしている人など、様々な事情で働けない状況にある人も対象となります。ただし、働ける状態になった場合は申し出る必要があり、正当な理由なく就労を拒否すると保護費が減額される場合があります。
また、外国籍の人でも永住者や日本人の配偶者である場合は保護の対象となる可能性があり、年金受給者であっても収入が最低生活費に満たない場合は生活保護を受給できます。重要なのは、世帯全員の収入や資産を活用しても最低生活費を下回っているという経済的な状況です。
最低生活費とは
最低生活費とは、厚生労働省が定める健康で文化的な生活を送るために必要な最低限の生活費のことです。
この金額は地域や世帯人数によって異なり、主に生活扶助(食費・光熱水費・被服費など)と住宅扶助(家賃・修繕費用)の合計額で構成されています。
例えば、東京23区内の単身者の場合、月額約13万円が最低生活費の目安となります(※1)。地域による物価や家賃相場の違いを考慮し、全国は6つの級地に分類され、都市部ほど級地が高く設定されています。
生活保護の支給額は、この最低生活費から世帯の収入を差し引いた差額となります。収入が全くない場合は、最低生活費の全額が支給されます。
※1出典:厚生労働省「最低生活費の算出方法(R5.10 )」参照:2024.12.11
2.生活保護でどこまでサポートしてもらえるか

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。収入、生活、医療、教育など、生活全般にわたる包括的な支援を受けられます。※2
①収入面
毎月の生活費として生活扶助費が支給され、家賃相当額として住宅扶助が支給されます。また、冬季には暖房費、子どもがいる世帯には教育扶助が加算されます。これらの扶助費は、世帯の状況や地域によって金額が異なり、収入がある場合はその分が差し引かれます。
②生活面
ケースワーカーによる定期的な訪問や相談支援があり、就労支援や生活習慣の改善指導も受けられます。また、引っ越しが必要な場合の費用や、家具・家電の購入費用なども、必要性が認められれば支給対象となります。
③医療費
医療扶助により、健康保険がなくても医療機関で診療を受けることができます。自己負担は原則として発生せず、入院費用や薬代、通院交通費まで保障されます。歯科治療や眼鏡の作成なども対象となります。
④障害者加算
障害のある方には、障害の程度に応じて障害者加算が支給されます。重度障害の場合は介護扶助も利用でき、ホームヘルパーの派遣や福祉用具の購入費用なども支給対象となります。
※2出典:厚生労働省「生活保護制度の概要等について」p.6参照:2024.12.11
3.精神疾患がある人が生活保護を申請する際のポイント

精神疾患があっても生活保護の申請は可能です。医療機関での診断や治療を受けながら、必要な支援を受けられます。申請時のポイントを確認し、適切な支援を受けましょう。
①医療機関に相談する
精神疾患による生活保護の申請では、医師の診断書が重要な役割を果たします。診断書には、病名、症状の程度、就労の可否、必要な治療期間などの詳細な記載が必要です。主治医に生活保護の申請を考えていることを伝え、現在の症状や治療の見通しについて詳しく記載してもらいましょう。
②生活保護以外の支援制度についても調べておく
精神障害者保健福祉手帳の取得や障害年金の申請、自立支援医療(精神通院医療)の利用など、複数の支援制度を組み合わせることで、より安定した生活を送ることが可能になります。また、地域の障害者就業・生活支援センターや精神保健福祉センターでは、就労や生活面での相談支援も受けられます。
③支援制度の利用は正当な権利だと考えること
精神疾患により働くことが困難な場合、支援制度を利用することは当然の権利です。病気や障害があることを理由に支援をためらう必要はありません。必要な支援を受けながら回復に向けて進んでいくことが大切です。福祉事務所のケースワーカーや医療機関のソーシャルワーカーに相談しながら、自分に合った支援を受けていきましょう。
4.申請の流れと必要書類

生活保護の申請は、本人や扶養義務者、同居の親族が行うことができます。申請前の相談から受給開始までの流れと、準備すべき書類について説明します。
①申請に必要な書類
基本的な書類として、印鑑(ゴム印は原則不可)、身分証明書、マイナンバーカードが必要です。収入関係では、給与明細(直近4か月分)、年金証書、各種手当の証書、預金通帳(記帳済み)を用意します。住居関係では、賃貸借契約書と家賃の領収書、所有物件がある場合は登記書類が必要です。また、健康保険証、障害者手帳、生命保険証書、自動車の車検証、借金がある場合は関連書類も必要となります。なお、書類が揃っていなくても申請は可能で、後日提出することもできます。※3
②生活保護申請の流れ
まず福祉事務所の窓口で相談を行い、面接相談員が生活状況や困窮状態を確認します。申請が必要と判断された場合、申請書類を提出します。申請後、ケースワーカーによる家庭訪問調査が行われ、資産状況などの詳しい調査が実施されます。審査期間は原則14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)で、結果は郵送か電話で通知されます。受給が決定すると、担当者から説明を受け、保護費の支給が開始されます。支給は通常、月初めに銀行振込か、窓口での受け取りとなります。※4
※3出典:札幌市「生活保護申請時に用意していただきたい書類等」参照:2024.12.11
※4出典:江戸川区「生活保護の申請・受給」参照2024.12.11
5.生活保護の疑問

生活保護に関する一般的な疑問について、特に収入の変動や医療機関の選択、就労時の対応などを解説します。制度を正しく理解して必要な支援を受けましょう。
①月によって収入が違う場合は足りない分だけがもらえるのか
精神疾患により収入が不安定な場合でも、柔軟な対応が可能です。体調の良い時期に働いて収入がある月は、その分を差し引いた金額が支給されます。体調が悪化して収入が減少した月は、最低生活費との差額が支給されます。毎月の収入申告を行うことで、その月の実態に応じた支給額が調整されます。
②自由に病院を選ぶことはできるのか
基本的に受診する医療機関は、生活保護の指定医療機関に限られます。生活保護の指定医療機関は、自治体のHPから確認することが可能です。ただし、高額な自由診療や保険適用外の治療は対象外となります。
③働けるようになったらどうしたらいいか
就労が決まったら速やかにケースワーカーに報告します。初月の給与が支給されるまでは生活保護を継続して受けることができ、給与支給後に保護費が調整されます。一度保護を停止した後に症状が再発した場合でも、再度申請することは可能です。以前の受給歴は新たな申請の妨げにはなりません。
6.生活保護のご相談はリライフネットへ

今回は、生活保護と精神病について解説しました。生活保護の受給に病名などは関係しないため、収入面で条件を満たす場合は、生活保護を申請することが可能です。
リライフネットでは、関東一都三県を対象にマンション、アパート、個室型シェアハウスなどの住居提供を行っております。行政・不動産事業者・職業紹介事業者・NPO・ボランティア団体などと連携しているため、迅速な住居提供が可能です。
また、生活保護の申請サポートや生活の基盤となる当座の住居の確保等、お気軽にご相談ください。リライフネットでは完全無料で電話、メール、LINEでの相談が可能です。
ご相談はこちらから