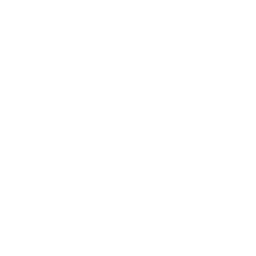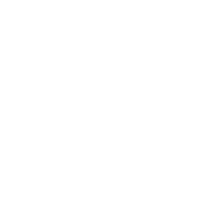目次
生活保護とは何か
日本国憲法第二十五条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と、社会権のひとつである生存権が保障されています。
同条第二項で、そのため国が施策を講じる義務があることを規定していますが、生活保護はその手段として、また日本の社会保障制度の根幹をなす制度として、極めて大きな役割を担います。
生活保護制度の趣旨は、「健康で文化的な最低限度の生活」を送るために必要な額として国が定める最低生活費と収入を比較し、収入でまかなえない分を扶助するというものです。この最低生活費は世帯員の年齢や人数、住む地域によって基準が異なります。
生活実態は人や世帯によって違いがあるため、生活扶助や住宅扶助をはじめとした8種類の扶助が必要に応じ支給されます。
生活保護を受けるときに必要な条件と書類
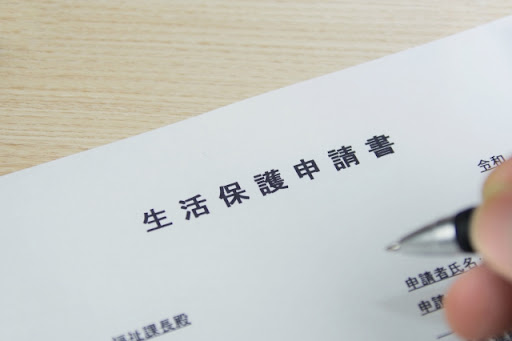
生活保護を受けるためには、世帯収入の合計額が最低生活費を下回るという条件をクリアする必要があります。日本における他の施策と同様、生活保護も世帯単位のため、世帯員のひとりだけ保護を受ける、またひとりだけ保護対象からはずすなど、個別の扱いはできません。
また生活保護は「最後のセーフティーネット」という位置付けであることから、働く努力をする、他制度による補助金や各種費用の減免を受けるなど、あらゆる努力をしなければならないという条件もあります。
実務上は「他法他施策の活用」といい、十分活用できていない場合はそちらを優先するよう指導されることがあります。
これらを踏まえ生活保護の申請をする場合は、都道府県や市区に設置される福祉事務所に保護申請の理由を記載した申請書を提出します。その際
・住民票や保険証など本人の状況を示す書類
・収入及び資産状況に関する申告書
・その他保護の要否判定に必要な事項を証明する書類
なども添付し、審査に必要な情報を福祉事務所に提供しなければなりません。
申請が受理されてから14日以内、もしくは30日以内に生活保護決定通知書か申請却下通知書が送付され、決定通知書を受けた場合に保護を受給することができます。
生活保護を受けるようになったら、様々な権利や義務が発生します。義務としては主に「生活上の義務」や「指示等に従う義務」があり、いずれも生活保護の「最低生活の保障」「自立促進」という目的を達成するために課せられています。
このうち生活上の義務は生活保護法第六十条に定めがあり、勤労の努力や健康維持、支出の節約など生活の維持向上に努めなければならないとされています。
また福祉事務所やケースワーカーからは、保護の目的達成に必要な指導や指示を受けることがあります。法第六十二条ではこの指導や指示に従う義務の規定があり、適切な理由がなく従わないときは、保護を受けられなくなることがあります。
保護の受給にデメリットはある?
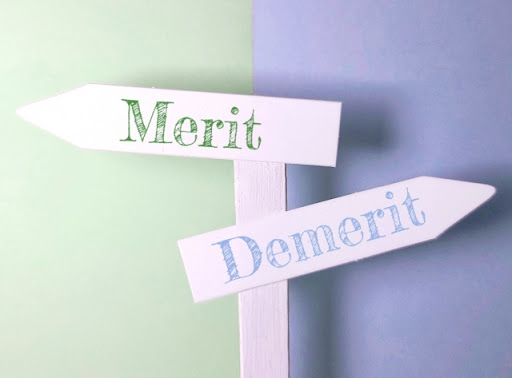
生活保護を受給するにあたっては享受できる権利に加え、受給者が守らなければならない義務や制限も規定されています。
本来デメリットという言葉は似つかわしくないのですが、保護を受けている人にとっては「デメリットに感じる」側面があるというのも事実です。
生活保護は「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度であるため、最低限度を超えるおそれのある部分を制限するという言い方ができます。資産や負債などの財産面での制約が主ですが、生活そのものに関するデメリットもあります。
生活保護で制限されることの範囲

一般の人と同様生活保護を受けている人も、日常生活を送る上で大きな制約はありません。しかし「最低限度の生活」という制度の趣旨から、様々な点が制限されています。
保護の申請時にも審査を受ける内容ですが、資産や高価な商品などの換金性の高いものは所有が制限されます。保護を受ける前にそれらを現金化し、売却して得た金銭で生活をしてくださいという理屈です。
中には万が一の場合に備え、保護費を節約しながらコツコツ貯金する人もいますが、預貯金の額が極端に多いとケースワーカーからの指導対象となり、保護の停廃止処分を受ける場合もあります。
生活保護を受けている人は、ローンやクレジットなどの借金をすることやその返済が認められません。借金を返済する分だけ生活に余裕があるという判断がなされ、借金相当分を収入認定されることがあります。ケースワーカーの指導指示に従わない場合は、最悪保護の停廃止を受けることもあるので注意しましょう。
また法律等で定められたものではありませんが、住む場所も事実上制限されます。生活保護には家賃相当分を支給する住宅扶助が含まれており、支給額には上限があるため高額家賃の物件に住むことができません。
ケースワーカーとの面談は何をするの?

生活保護に関するネット記事では、ケースワーカーとの定期的な面談をデメリットに分類しているものが散見されます。ケースワーカーの立場でとらえる面談は「生活の実態調査」ですが、保護を受けている人にとっては「日頃の悩みを相談するチャンス」と言い換えることもできるのです。
面談は主に、保護を受けている人の家庭を訪問しますが、場合によっては役所の窓口や入院中の病院など、実態に応じて場所が設定されます。
面談と言っても、堅苦しくとらえる必要はありません。特に訪問による面談は「茶飲み話」的なとらえ方をして、肩の力を抜いて普段どおりの受け答えをすれば十分です。
面談では日常生活の状況確認に加え、世帯の状況に応じた事項の確認が行われます。相談したいことがある場合は、このときに行うとスムーズに相談できるでしょう。
例えば高齢者世帯の場合は、介護保険サービスの利用状況や通院状況など、世帯員の心身状態を重点的に聞き取ります。また稼働年齢層がいる世帯では、ハローワークの利用状況や知人のつてによる求職活動など、法で定める「働くための努力」をしているかが確認されます。
面談自体を拒否することはできませんが、収入をはじめ世帯の状況が変わった際にこまめな報告をすれば、確認事項が減るため面談の時間を短縮することが見込めます。
親族にバレずに生活保護は受給できるのか
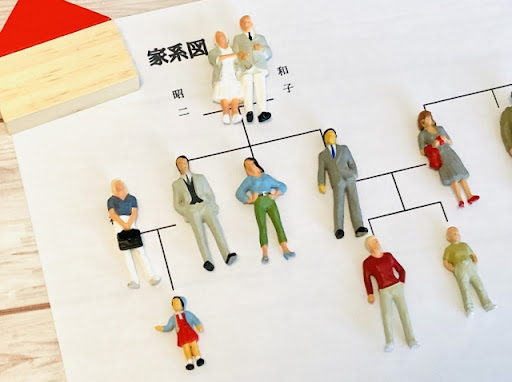
生活保護を受けていることや申請中であることを親戚に知られたくないという人にとっては、そのことがバレるということをデメリットに感じるかもしれません。しかし結論を言うと、親族にバレず生活保護を受けるのは原則として難しいと考えられます。
民法第八百七十七条第一項では、直系血族及び兄弟姉妹間の扶養義務があるとされており、同条第二項には家庭裁判所の判断で三親等以内に範囲を広げることができるという規定もあります。
生活保護の申請時には、扶養を受けられる可能性があるかを判断するため、原則として上記対象者に扶養義務の照会を行います。照会文書により保護申請していることがわかるため、隠すことは後述の場合を除き難しいと言わざるを得ません。また扶養する見込みが全くないと判断された場合を除き、扶養義務照会は定期的に行われます。
扶養の見込みが薄いのに照会する事例もあることから、従来の取り扱いが緩和される動きもあります。扶養義務照会を実施する対象は実情に応じて判断され、照会を行わない事例も増えてきていることから、気になる人は支援団体に相談してみましょう。
通常3親等以内の親族がいない人でもなければ、生活保護を申請していることや受けていることは必ず知られる、と考えておきましょう。
生活保護を受給する前にまずは相談を

生活保護を取り上げているネット記事では、デメリットをあたかも悪いことのように表記するものが散見されますが、生活の保障と自立の促進という生活保護本来の目的を考えるとやむを得ないと言えます。
また生活保護は最後の砦としての制度であり、事前にあらゆる策を講じる必要があります。そのための調査や照会をデメリットととらえる人がいるかもしれません。
一概にデメリットと判断する前に、相談機関で十分な説明を受け納得してから生活保護を検討したいところですが、相談先としておすすめなのがリライフネットです。
リライフネットは生活困窮者サポートの専門家として相談者が持つ問題点を整理し、生活保護のメリットやデメリットを詳しく教えてもらうことができます。
相談も完全無料なので、生活に困窮する人はリライフネットに生活保護の相談をしてはいかがでしょうか。