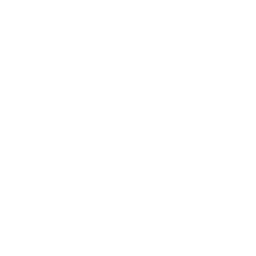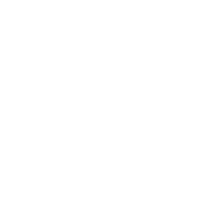生活保護を受給していると住宅扶助といって家賃に対するお金がもらえる制度があります。
住宅扶助は家賃に使うものですが、もし滞納してしまったらどうなるかお話していきたいと思います。
生活保護受給者の方は、もしもの時のために目を通しておいて損はありません。
目次
1.生活保護受給者が家賃の滞納をした場合どうなるのか

安定した住居を手にすることと引き換えに家賃は必ず貸主の方に支払わなければならないものです。
生活保護受給者の方が家賃を支払い忘れるとどのようなことがおこるのか、解説していきます。
①住宅扶助の返還
生活保護とは、国民に憲法25条の規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する制度です。
この制度は生活や教育など様々な面で援助を行い、住宅の確保も「住宅扶助」として対象の一つになっています。
日本全国で住宅扶助の上限額は異なり、地域や世帯数によって定められています。
住宅扶助は住んでいるアパートなどの家賃の支払いにあてる為のものです。
決まりとして住宅扶助を家賃以外の生活費などに充てることは許されていません。
そのため家賃を滞納した時は住宅扶助を指定以外のことに使用したということで、福祉事務所に返還をしなければなりません。
もちろん大家さんや貸主さんにも滞納している家賃を支払わなければならないので二重に家賃分の費用がかかることになります。
②強制退去
強制退去と聞くと大げさに聞こえるかもしれません。
ですが、家賃を3ヶ月続けて滞納すると強制退去となる可能性があります。
まず1ヶ月家賃を滞納すると貸主の方から督促の連絡がきたり書面が届くことが多いです。
この時点ですぐに支払うのが得策ではありますが、その後2ヶ月、3ヶ月と滞納を続けると3ヶ月の時点で貸主は賃貸契約を解除することができると有力な判例があります。
その後、内容証明郵便で契約解除通知が届くのが一般的でしょう。
さらにその後も滞納を続け、契約解除に承諾しない場合には裁判所へ訴訟され明け渡し請求というものが届きます。
明渡判決が行われると原則として強制退去となります。
その間家賃の支払いにあてていなかった住宅扶助は福祉事務所から返還を求められ、住む家もなくなってしまいます。
貸主さんや福祉事務所など関わる人の信頼を無くす行動でもあるので、家賃は滞納しないように気をつけることが大事です。
2.生活保護受給者が家賃を滞納してしまった場合の対処方法

家賃を滞納してしまった場合、一日も早い対処が必要です。
まず家賃をどれぐらい滞納しているのかを把握しましょう。
自分一人では抱えきれなかったり不安が強いこともあるかもしれません。その場合はケースワーカーや専門家に相談することが安心です。
ただしケースワーカーに相談しても家賃を肩代わりしてくれたり、滞納した家賃を返済するための一時扶助などの制度はありませんので注意しましょう。
住宅扶助を家賃以外に使用してしまったということを知られることになるので、住宅扶助の返納を求められますが正直に話すことが得策です。
ケースワーカーや専門家に相談し、貸主さんに滞納家賃を返済、今後も住み続けられるための交渉を行うことがベストでしょう。
滞納した家賃は分割で返済するなど、ケースワーカーや福祉事務所と相談し必ず返済できる方法を考えましょう。
3.生活保護受給者が家賃の未払いを事前に防ぐ方法
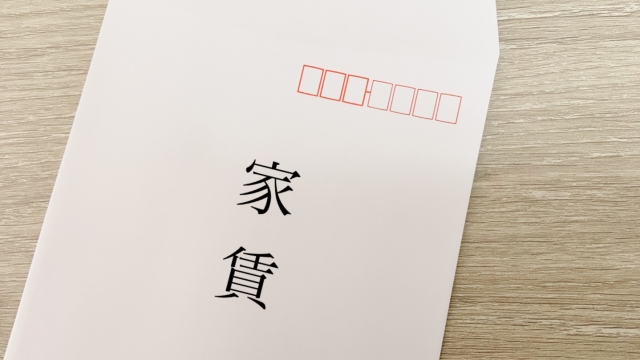
家賃の滞納をすると、住宅扶助の返済や退去の可能性などがあり、生活が成り立たなくなってしまいます。
そうなる前に事前に防ぐ方法があります。それは「代理納付」という方法です。
代理納付とは福祉事務所が生活保護受給者に代わって貸主に納付する制度です。
本来、住宅扶助は生活費を賄う生活扶助と合わせて受給者に支払われます。
その中から家賃分を貸主に振り込むという手間もなくなり、生活扶助と間違えて住宅扶助に手をつけてしまうという可能性も失くすことができます。
代理納付は福祉事務所で代理納付を申し込む書類を提出することで制度を使用できます。
代理納付という方法を使うことで、家賃と共益費を滞納してしまう心配がなく生活することができるのです。
ただし、代理納付はすでに滞納してしまった家賃を代わりに支払ってくれる制度ではありません。すでに滞納してしまっている家賃についてはケースワーカーや専門家に相談し解決するようにしましょう。
4.強制退去になってしまった場合はどうするべきか

万が一、強制退去となってしまった場合は次の転居先を探しましょう。
明渡し請求が届くと強制退去までは多くの時間はありません。ホームレスにならないためにもスピーディな対応が求められます。
では次の物件はすぐに見つけることはできるのでしょうか?
答えは難しいと言わざるを得ません。その理由を解説していきます。
①強制退去になった情報は共有される
大家さんと直接契約ではなく、不動産会社など仲介をした場合や保証人の代わりに保証会社を利用した場合は家賃を滞納したという情報は信用情報として記録されます。
そのため新しく物件を探しても、審査のときに審査が通らないという可能性が高いです。
審査が通らなかった場合は、大手の不動産会社を使わない・独立系の保証会社を使うことで信用情報の共有がされておらず審査が通る可能性もあります。
審査が通って物件が借りることができたら、次は滞納を繰り返さずに代理納付制度を利用するなどして必ず家賃を支払うようにしましょう。
②連帯保証人を用意する必要がある
保証会社の信用情報の共有により、審査が通らない可能性があるとお話しましたが保証会社を利用せずに安定した収入のある連帯保証人を用意することで保証会社を使わずに審査を通すことができる可能性もあります。
ただ、生活保護は扶養義務者が居ない人が受けられる制度です。そのため安定した収入のある連帯保証人を用意することは難しいといえるでしょう。
③初期費用がかかる
新しい物件が決まったとしても、入居時には多額の初期費用がかかります。
転居先の敷金礼金や引っ越し費用などは家賃数か月分の金額になることが多いでしょう。
通常の引っ越し時と同じく敷金礼金や引越し費用は一時扶助として受け取ることができる可能性もありますが、福祉事務所の判断によるでしょう。
このように強制退去になると様々な問題がふりかかります。
通常、強制退去までは6ヶ月程の猶予があると考えられています。
その間に家賃支払い催促の時点で対応し誠実な対応をとることが大切です。貸主や保証会社、不動産会社の信用を失わないように気をつけましょう。
5.まとめ

生活保護を受給している人が家賃滞納したらどうなってしまうのか?という疑問についてお話してきました。
家賃を滞納してしまったら一日も早い対処が必要です。
先延ばしにしたりせずにすぐにケースワーカーや専門家等に相談しましょう。
強制退去になってからでは、新しい物件を探すことは簡単なことではありません。
家賃の支払いを忘れてしまいそう…と不安のある方は「代理納付」制度を活用しましょう。
福祉事務所が家賃を貸主さんに振り込んでくれる制度です。
自分で管理する能力をつけることも大事なことですが、病気や障害があり思うように管理することができない方もいらっしゃいます。
まずは治療や療養に専念し、重要な管理はお任せしてみてもいいかもしれません。
リライフネットでは生活保護を受給している方の家賃の滞納や代理納付についてなど専門的な相談に対応できます。
また、強制退去になった方でも提供可能な物件を用意しています。
一人で悩まずに、ぜひお気軽にお問い合わせお待ちしています。