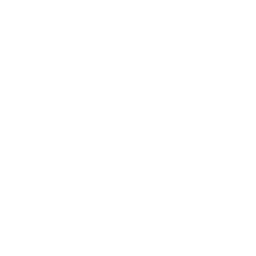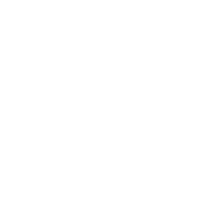収入が減少し生活が困難になった場合や、ケガや病気で収入が途絶えた際に、問題となるのが家賃です。
家計の大きな割合を占める家賃は、生活保護を受給した場合、無料になるのでしょうか?
今回は、生活保護を受給した場合に家賃が無料になるのか、家賃が支給されるとしたらどのくらいの金額なのか、どのような支給条件があるのかなどを解説します。
1.生活保護を受給すると家賃は無料?

生活保護を受給した場合、家賃は無料にはなりませんが、生活保護費から実費が支給されるため自己負担分はなくなります。
①生活保護とは
生活保護を簡単に説明すると、生活が一時的に困難になった国民に対して、最低限の生活を国が保障する制度です。
生活保護法第一条には、次のように定められています。
「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障する」
引用:e-GOV「生活保護法」第一条(参照2023.08.11)
また、生活保護法は、日本国憲法第二十五条の第一項「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
※1出典:厚生労働省「ナショナルミニマムに関する議論の参考資料 」P.2
という理念に基づき制定された法律です。
そのため生活保護法には、最低限度の生活を維持するための扶助が複数定められています。
生活が困窮した場合に生活保護を申請し、それらの扶助を利用することは、すべての国民の権利として認められています。
②生活保護を受給すると家賃はどうなるのか
生活保護を受給すると、家賃は住宅扶助という厚生労働省が定める扶助に区分され、規定の範囲内で支給されます。
規定の範囲内の家賃であれば、全額支給されるため自身が負担する金額はありません。
しかし、現在の家賃が、生活保護の住宅扶助基準となる金額よりも高い場合は、引っ越しが必要になる可能性が高いといえます。
基準を超えている分の差額を支払えば良いという簡単なものではなく、生活保護の基準と照らし合わせて、引っ越しの有無が判断されます。
住宅扶助による家賃の支給方法は自治体によって変わります。現金として口座に支給された住宅扶助を、自身で家主に支払うケースと、福祉事務所から直接家主へ支払う「代理納付」があります。
(※万が一生活保護費の返還金が発生した場合は住宅扶助のお金も返還対象になるので要注意!)
2.生活保護の条件と免除されるもの

①生活保護の条件
生活保護の条件については、厚生労働省が以下のように詳しく説明しています。(※2)
生活保護の条件の確認は、世帯単位で行われ、生活保護を受給する前に、世帯員全員が家や車、土地など利用できる資産を全て活用して生活することが前提とされています。
また、扶養義務者がいる場合は、生活保護よりも扶養義務者の扶養が優先されます。
その上で、生活が困難な場合に生活保護の申請が可能になります。
最終的には世帯収入と厚生労働大臣が定める最低生活費を比較し、不足している部分に生活保護が適用されます。
※2出典:厚生労働省「生活保護制度」(参照2023.08.11)
②生活保護で免除されるもの
生活保護受給中は、自己負担がなく支払いが免除されるものが、厚生労働省によって、以下の8つの扶助として区分されています。(※3)
【生活扶助】
食費、被服費、水道光熱費など、日常生活に必要な費用が受けられます。
【住宅扶助】
家賃が基準の範囲内で実費で支給されます。
住宅の修繕費や引っ越しの初期費用など一時的な費用も基準の範囲内であれば支給されます。
【教育扶助】
基準の範囲内で義務教育の学用品費が支給されます。
【医療扶助】
医療費は、医療扶助が適用されるため、本人の窓口負担はありません。
【介護扶助】
介護サービスを利用する場合、介護扶助が適用され本人負担はありません。
【出産扶助】
基準の範囲内で実費が支給されます。
【生業扶助】
就職のための資格取得などが、基準の範囲内で支給されます。
【葬祭扶助】
基準の範囲内で埋葬費用などが実費で支給されます。
※3出典:厚生労働省「生活保護制度」(参照2023.08.11)
③その他の免除
生活保護受給中は、8つの扶助以外にも免除になるものとして、厚生労働省が以下の内容を定めています。(※4)
生活保護世帯は非課税世帯となるため税金が免除されます。
【所得税・住民税】
生活保護受給中の世帯は、所得税や住民税が免除となります。
【国民健康保険】
生活保護受給中は、国民健康保険に加入できなくなります。
そのため保険料の支払い義務もなくなります。
国民健康保険は利用できませんが、医療扶助が適用されるため、医療費の窓口支払いはありません。
※4出典:厚生労働省・援護局保護課「生活保護基準の見直しに伴いた制度に生じる影響について」P.16-17平成30年1月19日
3.生活保護でもらえる住宅扶助とは

生活保護受給中の家賃は、住宅扶助として支給されます。
家賃の具体的な支給額は、厚生労働省の定める住宅扶助の基準を元に計算します。
①住宅扶助とは
住宅扶助は、厚生労働省が「住宅扶助について」の中で、以下のように定義しています。
「住宅扶助は、困窮のために最低限度の生活を維持することのできない者に対して、家賃、間代、地代等や、補修費等住宅維 持費を給付するもの。」
引用: 厚生労働省社会・援護局保護課「住宅扶助について」p.1 平成25年11月22日
生活保護の基準は、「最低限度の生活を維持する」ための扶助であるため、支給される金額は規定の範囲内となります。
②住宅扶助の上限金額
具体的に、いくらの家賃までが支給されるのかは、厚生労働省が定める「級地」と呼ばれる土地の区分や世帯人数によって変わります。
住居のある土地が、どの級地に当たるのかは、厚生労働省の定める「級地区分」で分かります。
下記「級地区分」のリストでは、都道府県と市区町村名で、住居の級地を調べられます。
厚生労働省は、平成25年に発表した「住宅扶助について」の中で、以下のような条件や住宅扶助の支給額を定めています。(※5)
住宅扶助では、家賃と住宅の補修費用などの維持費、転居時に必要になる敷金、礼金、火災保険料などの一時的な費用や契約更新料などが支給されます。
「特別基準上限額」が定められています。
特別基準上限額は、東京23区の単身世帯の場合、1級地の区分となるため53,700円です。
さらに、世帯人員の人数によって特別基準が適用されます。
世帯人員が6人以下では、限度額×1.3、7人以上では限度額×1.3×1.2を上限として、支給されます。
※5出典:厚生労働省 社会・援護局保護課「住宅扶助について」平成25年11月22日 資料4
4.生活保護の家賃補助を受けるときの注意点

①家賃補助の範囲内の住居を探す
現在の家賃が生活保護の基準を超えている場合、基準を満たす物件を探す必要があります。
しかし、生活保護受給中は、住宅の審査が厳しくなる傾向があり、物件探しは困難です。
不動産会社側は「家賃が確実に支払われるのか」という点を重要視しています。
そのため家賃補助が直接家主側へ支払われる「代理納付」であれば、支払いが確実と判断され、比較的審査が通りやすくなります。
不動産会社には、生活保護を受給予定であることや受給中であること、家賃の上限などを事前に伝えて物件を探します。
②家賃補助は実費が支給される
家賃補助は基準の範囲内で実費が支給されます。
例えば、東京23区の単身世帯の基準額は53,700円ですが、実際に入居した住居の家賃が49,000円の場合は、49,000円のみ支給されます。
③定期的な生活保護の見直し
生活保護は、定期的に見直しがされています。
生活扶助は、物価高騰により2023年10月に見直しが予定されているため、住宅扶助も必要に応じて見直しされる可能性があります。
生活保護関連の情報は、時々チェックしておきましょう。
5.まとめ

今回は、生活保護受給中の家賃について解説しました。
生活保護受給中の家賃は、住宅扶助として支給されます。
家賃の上限は、住居のある場所(級地)と世帯人数によって変わります。
現在の住居が、家賃補助の上限を越えてしまう場合は、引っ越しが必要になります。
生活保護受給中の物件探しは、審査も通りにくく、家賃の制限もあるため困難です。
リライフネットの運営法人は、東京都や千葉県指定の居住支援法人として、住居に関する悩みやお困りごとを解決しています。
無料で相談が可能なリライフネットでは、生活保護受給中の物件探しもサポートしています。
お気軽にお問合せ下さい。